
今回は、「グローワイヤー試験(Glow Wire Test)」という、
ちょっとマニアックだけどめちゃくちゃ大事な安全試験についてお話しします。
実はこの試験、火災事故を防ぐために欠かせない試験なんです。
電気製品の開発や設計に携わるなら、絶対に知っておきたい試験の一つです。
それでは、火花バチバチ、ワイヤーじゅうじゅう…そんなスリル満点(!?)
グローワイヤー試験を一緒に覗いてみましょう!

なぜ「グローワイヤー試験」が必要か?
たとえば、あなたが家電のエンジニアだとしましょう。
毎日何千回もオンオフされるスイッチ、常に電気が流れる基板。
ある日、ほんのちょっとしたトラブルで、内部のプラスチック部品に過電流が流れたら…?
そう、発熱 → 発火の危険があるんです。

こうしたリスクを想定して、「火がつきそうな部品」に
疑似的な熱源を当てて、安全性をチェックする試験。
それがグローワイヤー試験です。
グローワイヤー試験って?
グローワイヤー試験は、
発熱した金属線(ニクロム線)を試験する部品に接触させて発火や燃焼のしやすさを評価する試験です。

試験のイメージ
ニクロム線を、750〜960℃まで加熱します
その熱々ワイヤーを、試験する部品に30秒間接触させます。
火がつくか?溶け落ちるか?炭化するか?を観察します。
ポイントは、火がついてもすぐに燃え広がらないかどうか。

安全な製品なら、たとえワイヤーが熱くても、
火がつかない or すぐに消える設計になっているんです!
事例「おもちゃのロボットに火が!?」
ある日、子供向けのロボットおもちゃの設計をしていたAさん。
かわいいロボットが音楽に合わせて踊る機能を搭載!
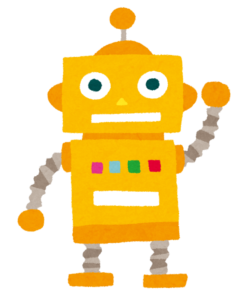
でも設計審査でNGが出たのです。
「部品の樹脂がグローワイヤー試験に通らなかった」と。
詳しく調べてみると、ロボットの部品に燃えやすい樹脂が使われていました。。。
そこで、部品の樹脂を燃え難いものに変更!
この改善によって、グローワイヤー試験をパス!
Aさんのロボットは子どもたちの手に届き、安全に遊んでもらえる製品になりました!

グローワイヤー試験の基準って?
試験は主にIEC 60695-2-10~13などの規格に基づいて行われます。
主な評価ポイント:
| 項目 | 合格の目安 |
|---|---|
| 発火時間 | 30秒以内に消火されること |
| 溶け落ちた粒 | 下に置いたティッシュに燃え移らないこと |
| 炭化範囲 | 広がりすぎないこと(設計により基準は異なる) |
つまり、「ちょっと火がついたくらいでは燃え広がらないこと」が超重要!
どんな製品で使われてる?
グローワイヤー試験が活躍するのはこんな製品
電気スイッチやコンセント
家電製品(電子レンジ、冷蔵庫など)
プラグ・コード類
自動車の電装品
おもちゃの電動部品
とくに「人の手が触れる or 火災につながりやすい場所」に使われる部品には、
必須の試験になっています。
まとめ:未来の製品は、あなたの「火の用心」から!
いかがでしたか?
グローワイヤー試験は、
製品が異常加熱しても燃え広がらないか
火災事故を未然に防ぐ設計ができているか
を確認する、非常に大切な試験です。
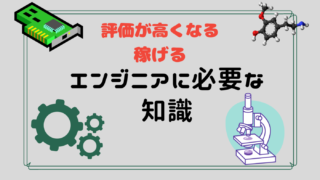
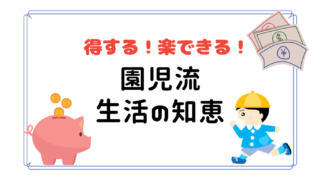
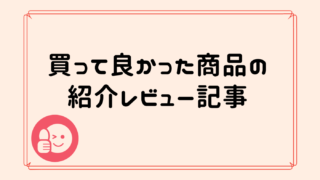
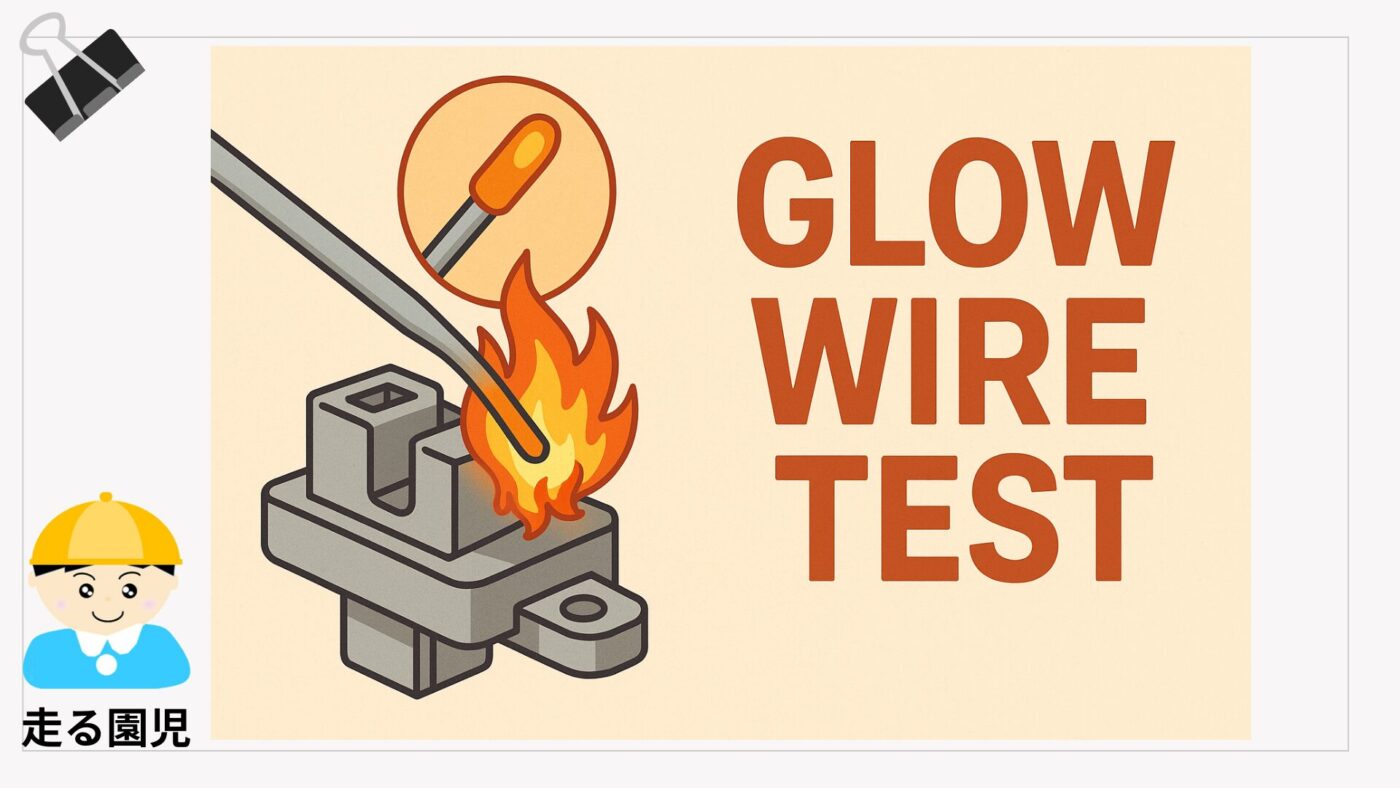
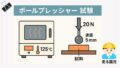

コメント