チクソ性を知っていますか?
液体の性質のことなのですが、知らない人も多いでしょうね。

チクソ性について分かりやすく解説します。
チクソ性
チクソ性(チキソ性)の正式名称はチクソトロピー性(チキソトロピー性)といいます。

長くて言い難いので、
一般的には『チクソ性』(チキソ性)と言われています。
チクソ性とは液体がもつ特殊な性質です。
私たちの周りにある液体には、
チクソ性がある液体とチクソ性が無い液体があります。
チクソ性とは
液体にはドロドロと流れにくいものもあれば、
サラサラと流れやすいものもありますよね。
チクソ性がある液体は、液体をかき混ぜたり振ったりと
ドロドロの液体に力を加えるとサラサラと流れやすくなり、
力をかけずにおくと、ふたたびドロドロの状態になります。

力によってドロドロになったり、サラサラになったりと
粘性が変化する液体の性質をチクソ性といいます。
身近なチクソ性がある液体
チクソ性があるものを紹介します
マヨネーズもチクソ性がある液体です。
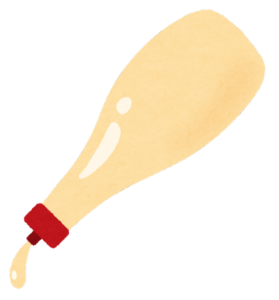
マヨネーズの蓋を開けて、容器を逆さにしてもマヨネーズはドロドロなので、容器から出てくることはありせんが、
容器を押したり、振ったりとマヨネーズに力を加えるとドロドロからサラサラになるため容器から出てきます。
容器から出てきたマヨネーズには力が加わらないので、再びドロドロの状態に戻ります。
お好み焼きにマヨネーズをかけた後は、ドロドロに戻るのでマヨネーズは広がることはありません。

その他のチクソ性がある身近なモノ
歯磨き粉

歯磨き粉もマヨネーズと同じような感じなので、イメージし易い身近なチクソ性があるものですね
ペンキ
ペンキもチクソ性があります。
ペンキメーカはわざとペンキにチクソ性があるペンキを開発製造しています。
刷毛で塗るときには力が加わるのサラサラに塗りやすくなり、
塗り終わって刷毛の力が加わらない状態ではドロドロになるので、
垂れ広がりにくくなります。
ペンキはチクソ性が大いに役立っています。
チクソ性はとても役に立つ性質なのです。
チクソ性の数値
チクソ性が大きいとか小さいとか定性的な表現は、個人差があるのでバラつくので、定量的な数値でチクソ性を表現することが求められます。
チクソ性は、『チクソ比』という数値で表すことができます。
チクソ比
チクソ比は次の式で求めることができます。
B型粘度計と呼ばれる液体をかき混ぜながら粘度を計測する計測器を用いて粘度を測定します。
かき混ぜる回転数を1rpm(1分間に1回転)と10rpm(1分間に10回転)の2種で粘度を測定した場合、チクソ性が高い液体は1rpmの粘度より10rpmの粘度の方がサラサラになるので、チクソ比の数値が大きくなります。
↓B型粘度計↓


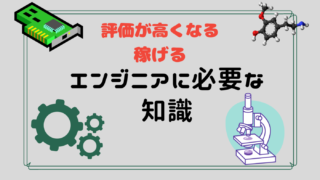
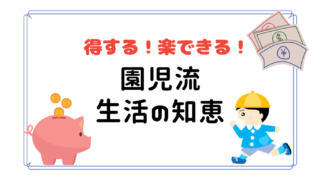
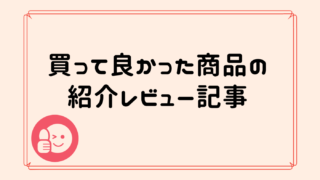
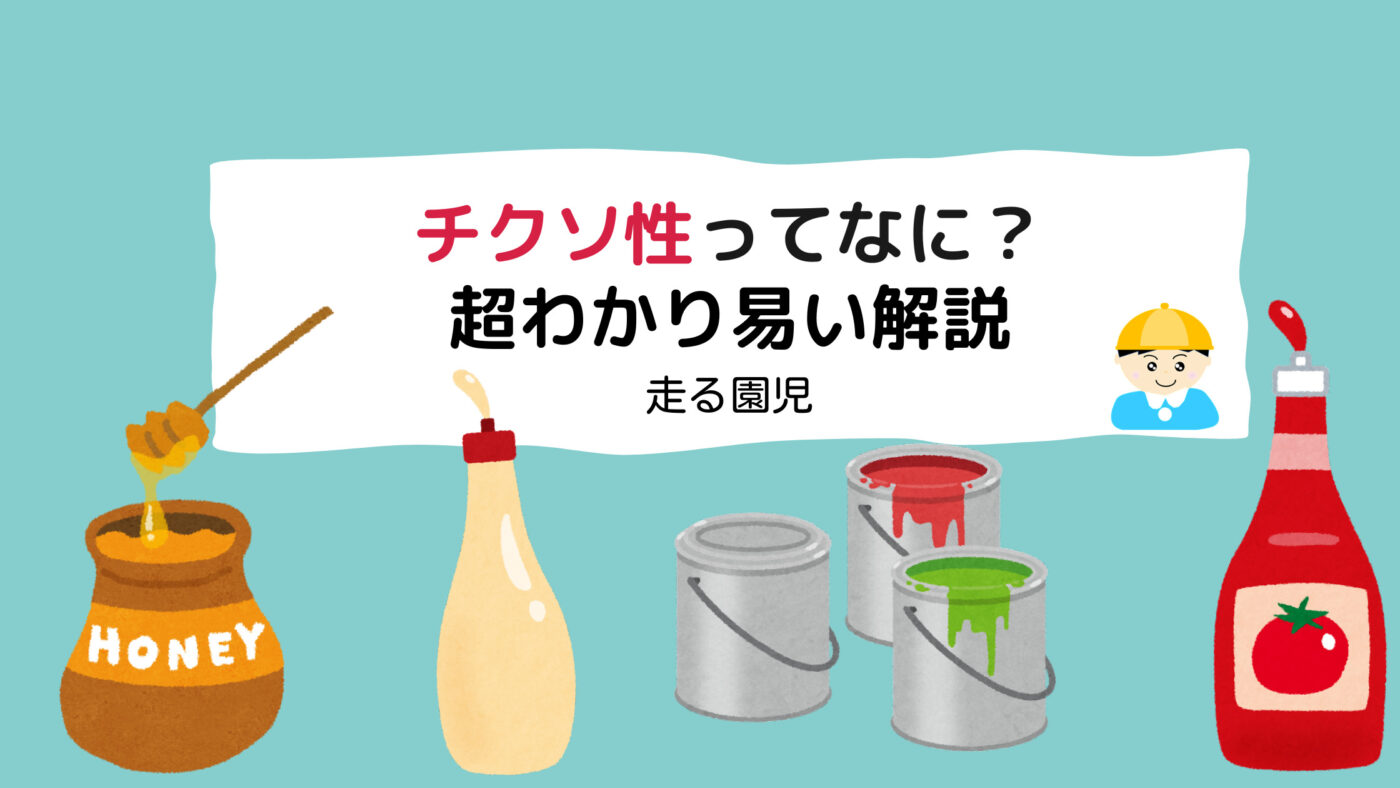



コメント