プラスチックは現代の製品に欠かせない素材ですが、一口に「プラスチック」と言っても、その種類は実に多様です。
材料や製品開発の現場、またはトラブル調査の場面で、「これ、何のプラスチックだろう?」と感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。
今回は、燃焼の状態(におい・色・炎・残渣など)から、プラスチックの種類を大まかに見分ける方法を紹介します。
あくまで目安としての簡易判別法ですが、材料に対する理解を深めるきっかけになるはずです!
🔥 プラスチックの燃焼テストとは?
プラスチックを火に近づけて燃やした際に起こる現象(燃え方・煙の色・におい・炎の色・残ったものなど)を観察することで、その種類を推定する手法です。
これは「簡易識別法」として、現場レベルでは昔から使われている知識です。
⚠️ 注意:実施する際は必ず換気の良い場所やドラフトチャンバー内で行い、火傷・有毒ガスに十分注意してください!
🔍 燃焼特性によるプラスチックの見分け方【代表例】
| プラスチック名 | 燃焼時の特徴 | におい | その他の特徴 |
|---|---|---|---|
| PE(ポリエチレン) | よく燃える、黒いすすを出す | ろうそくのようなにおい | 炎は黄色く、煙多め |
| PP(ポリプロピレン) | PEに似てよく燃える | 甘いにおい(パラフィン系) | やや青っぽい炎になることも |
| PS(ポリスチレン) | 明るい炎で勢いよく燃える | 甘く刺激的なにおい(スチレン臭) | 煙が黒く多い |
| PVC(ポリ塩化ビニル) | 炎に近づけると燃えるがすぐ消える | 塩素臭(焦げたゴムのようなにおい) | 有毒なHClガス発生。煙が白っぽい |
| PET(ポリエチレンテレフタレート) | 炎に入れると縮むがあまり燃えない | 甘く焦げたようなにおい | 溶けながら変形、灰が残りやすい |
| PA(ナイロン) | ゆっくり燃える、糸を引くように溶ける | 焦げた毛・たんぱく質のようなにおい | 黒い煤は少ない |
| PC(ポリカーボネート) | 燃えにくく、すすが少ない | やや薬品臭 | 燃えながら割れやすい、灰が残る |
👨🔬 どんな場面で役立つ?
古い製品の材料調査(図面や仕様書がないとき)
リバースエンジニアリングや素材選定の参考
材料トラブル(例:焼損)の初期調査
学生実験や技術教育の一環として
✅ 判別のコツと限界
この方法はあくまで「目安」です。同じPEでも添加剤や着色によって燃焼特性が変わることもあり、複数素材が混ざっている場合には判別困難になります。正確な判定にはFT-IR分析やGC-MS、元素分析などの機器分析が必要です。
ただし、燃焼テストによる大まかな識別スキルは、現場での材料対応力を高める武器になります!
🧪 おすすめのやり方(安全第一)
小さな試料をピンセットで持つ(もしくは金属トレイに置く)
アルコールランプやライターなどで着火
燃え方・におい・煙などを観察(短時間に留める)
完全に消火してから残渣の様子を見る
まとめ
プラスチックの燃焼状態から種類を見分ける方法は、化学や材料に携わる人にとって、意外と役立つ知識です。安全に配慮しつつ、身近な材料の性質に目を向けてみると、新たな発見があるかもしれません。
「燃えるか、燃えにくいか」「においはどうか」「残るものは何か」——
五感を使ってプラスチックと向き合ってみましょう!
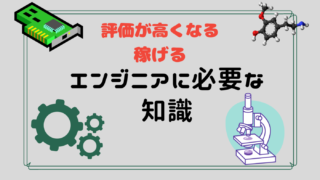
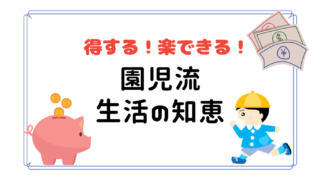
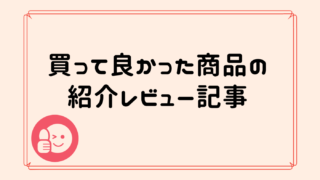
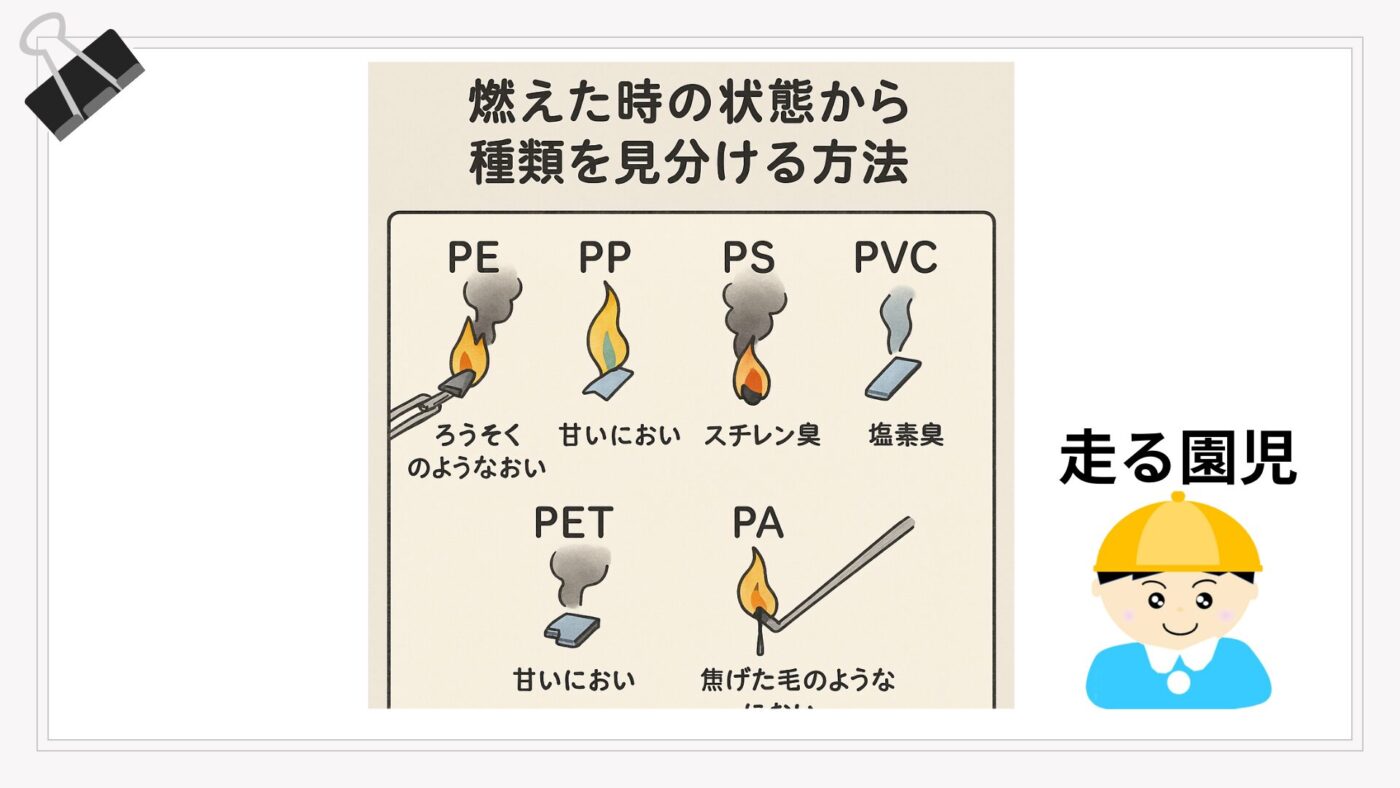


コメント